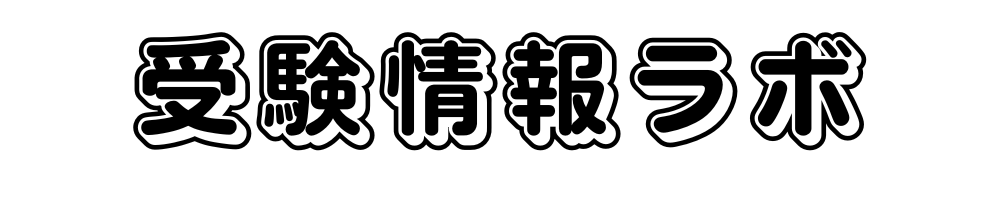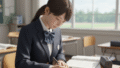私立高校の授業料無償化が、2025年、2026年にかけて大きく変わります。この記事では、所得制限がなくなる国の新しい制度について、いつから適用されるのかを整理しました。「うちの家庭は対象になる?」「結局いくらかかるの?」といった疑問に答えます。学費の負担について、不公平だと感じずに納得して学校を選ぶための判断材料がわかります。
- 2025年と2026年の制度変更点とスタート時期がわかります。
- 国と自治体で、支援額がどう違うのかを把握できます。
- 対象になる費用とならない費用、注意点が理解できます。
私立高校 無償化の最新情報と全体像
- 私立高校の授業料無償化はいつから?
- 2025年、2026年の詳しい動向
- 全国での実施状況と地域による違い
- 制度を先行実施した大阪府の動向
私立高校の授業料無償化はいつから?
国の公式資料によると、2025年4月から新しい制度が段階的に始まります。まず、国の「高等学校等就学支援金」の基準額である11万8,800円(公立高校の年間授業料に相当)が、全ての世帯に支給されるようになります。これにより、この基準額についての所得制限が事実上なくなると説明されています。
さらに2026年度からは、私立高校に通う生徒向けの加算額についても所得制限をなくす方針です。全国の私立高校の平均授業料にあたる45万7,000円を上限として、支援金が支給される予定です。
用語メモ|就学支援金とは?
高校の授業料にあてるための、国からの支援金です。現金が家庭に直接振り込まれるわけではありません。原則として、国から学校へ支払われ、授業料から差し引かれる仕組みになっています。
申請の時期と方法
申請は、高校入学後の4月に学校を通して行います。手続きは、オンライン申請システム「e-Shien」を利用できると案内されています。
ポイント:無償化の対象は、主に授業料です。入学金や教材費、通学にかかる費用などは、基本的に自己負担になるので注意しましょう。
2025年、2026年の詳しい動向
2025年度は、まず全世帯に基準額11万8,800円が支給できるようになります。これにより公立高校は実質無償化となり、私立高校はこれまで通り、所得に応じて支援額が加算される仕組みが続く見込みです。
そして2026年度には、私立高校向けの加算額についても所得制限がなくなります。上限額も45万7,000円に引き上げられる方針で、全国的に私立高校の授業料が実質無償化に近づくと考えられています。
比較表|制度の主な変更点(全日制の例)
| 年度 | 所得制限 | 国の基準額 | 私立加算(上限) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024まで | 有(目安:910万円) | 11万8,800円 | 年収590万円未満で39万6,000円 | 対象や加算は所得に応じて段階的 |
| 2025 | 事実上撤廃(基準額) | 11万8,800円(全世帯) | 従来枠を踏襲(自治体上乗せ有) | 先行措置としてスタート |
| 2026 | 撤廃(私立加算) | 11万8,800円 | 45万7,000円(全国平均相当) | 私立授業料の実質無償化に近づく |
出典の一例:文部科学省 令和7年度先行措置/三党合意概要
授業料以外の支援はある?
授業料以外の教育費については、返還が不要な「高校生等奨学給付金」という制度があります。この制度は、生活保護を受けている世帯や住民税が非課税の世帯が対象です。公式サイトによると、例えば全日制高校の場合、生活保護世帯には公立で3万2,300円・私立で5万2,600円、非課税世帯には公立で14万3,700円・私立で15万2,000円が支給されると示されています。
全国での実施状況と地域による違い
国の制度は全国共通で適用されます。しかし、お住まいの自治体が独自に上乗せ支援をしているかどうかで、家庭が実際に負担する金額は変わってきます。例えば東京都は、2024年度から国の制度に先がけて私立授業料の実質無償化をスタートしました。都内の私立高校の平均授業料である約48.4~49万円を上限に支援しています。
確認のコツ:自治体の上乗せ額や対象になる条件、申請方法は毎年変わる可能性があります。必ずお住まいの自治体の公式サイトで、最新の情報を確認するようにしましょう。(例:東京都制度案内)
実際に高校でかかる費用はどれくらい?
文部科学省の調査では、授業料以外も含む高校初年度にかかる費用の目安が公表されています。公式PDFによると、高校(全日制)1年間でかかる学習費の総額は、公立で約59.8万円、私立で約103.0万円という結果でした。
注意:「無償化」といっても、自己負担がゼロになるわけではありません。入学金、施設費、通学費、制服・教材費、部活動費、ICT端末の購入費などは、別途準備が必要です。
自治体の情報を早く正確に見つける方法
自治体の制度案内は、公式サイトのどこにあるか分かりにくいことがあります。そんなときは、検索サイトで「(都道府県名) 高校 授業料 支援金 上乗せ」のように入力して探すのが近道です。検索結果の中から、URLの末尾が「pref.xx.jp」や「metro.tokyo.lg.jp」など、都道府県の公式サイトを優先して開きましょう。ページを開いたら、パソコンならCtrl+Fキーでページ内検索を使い、「対象」「上限」「申請」といった言葉で確認するとスムーズです。PDF資料が複数ある場合は、発行日が新しいものから読むのがポイントになります。
モデルケースで見る負担額の試算例
| ケース | 授業料(年額) | 就学支援金(国) | 私立加算(上限想定) | 自治体上乗せ(例) | 自己負担額 | 留意点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立・上限内 | 450,000 | 118,800 | 331,200 | 0 | 0 | 授業料は実質ゼロでも、入学金などは別途必要 |
| 私立・上限超過 | 520,000 | 118,800 | 331,200 | 30,000 | 40,000 | 差額は自己負担。上乗せ支援で一部軽くなることも |
| 公立 | 118,800 | 118,800 | — | — | 0 | 通学費や制服代などの負担が相対的に大きい |
注意:この表は、制度を理解するための簡単な例です。実際の金額や上限、上乗せ支援の有無は、年度・地域・学校によって異なります。必ず公式サイトなどの一次情報で確認してください。
私立高校 無償化の注意点
- 対象になる費用、ならない費用
- 入試への影響と学校選びのポイント
- 「おかしい」「不公平」という声について
- まとめ:最新情報の確認先
対象になる費用、ならない費用
就学支援金の対象は、原則として授業料のみです。入学金、施設整備費、教材費、制服代、通学費、部活動費などは、支援の対象外だと説明されています。
こうした授業料以外の教育費の負担を軽くする制度として、「高校生等奨学給付金」があります。公式サイトによると、この給付金の対象や金額は、世帯の状況(生活保護か、住民税が非課税かなど)や、通う学校の種類によって異なります。
事前に確認したいチェックリスト
- 学校の学費内訳(授業料はいくら?入学金は?)
- お住まいの自治体の上乗せ支援(対象になるか?上限は?)
- パソコン購入や通学定期代など、最初にかかる費用の見積もり
- 奨学給付金の対象になるか、申請はいつまでか
入試への影響と学校選び
制度が拡充されることで、私立高校を志望する生徒が増える可能性が指摘されています。各種の報道や解説では、私立高校が選びやすくなる一方で、専門学科のある公立高校や地域の高校の志願者動向に変化が出るかもしれない、という点も議論されています。
「おかしい」「不公平」という声について
制度の対象が広がる一方で、住んでいる地域や家庭の所得によって負担感が違うことから、「おかしい」「不公平だ」と感じる声もあります。国会の資料でも、特定の学校に志願者が偏る可能性や、専門高校への支援の必要性などが議論されています。そのため、授業料以外の費用に困っている低所得世帯への支援を厚くすることや、地域の高校の教育環境を整えることが重要だと説明されています。
留意点:自治体独自の上乗せ支援は、その地域の財源や教育方針によって差が出ます。同じ年度でも、住んでいる場所によって負担感が異なることは、知っておく必要があります。必ずお住まいの自治体の最新情報を確認してください。
まとめ:最新情報の確認と参考リンク
- 2025年からは、まず基準額11万8,800円が全世帯に支給されます。
- 2026年からは、私立高校向けの上乗せ額が上限45万7,000円に拡充される方針です。
- 所得制限がなくなることで、対象が全国の全世帯に広がります。
- 無償化の対象は主に授業料で、入学金や通学費は自己負担です。
- お住まいの自治体の上乗se支援があるかないかで、実際の負担額は大きく変わります。
- 東京都は平均授業料相当の支援を先行実施し、大阪府は完全無償化を目指す方向です。
- 申請方法や締切は、オンライン申請システム「e-Shien」の最新案内を確認しましょう。
- 授業料以外の費用には、奨学給付金という別の制度があります。
- 県外の学校に通う場合は、お住まいの自治体のルールをよく読んでください。
- 入試への影響は様々な要因が絡むため、数年間の動向を見ることが大切です。
- 学費の見積もりは、支援金で引かれる額と、実際に支払う額を分けて管理すると分かりやすいです。
- 学校独自の奨学金制度なども確認しましょう。
- もし家計が急変したときは、すぐに学校に相談することが第一です。
- 根拠となる情報は、必ず国や自治体、学校の公式サイトで確認する習慣をつけましょう。
公式情報・参照リンク