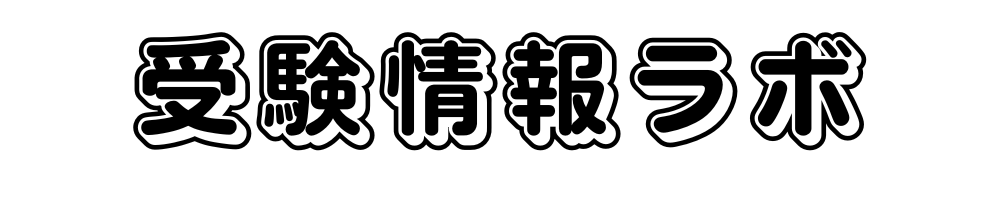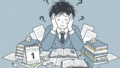2026年度から年内学力入試が本格化し、大学受験が大きく変わります。年内学力入試がどのように位置づけられているのか、年内学力入試が注目されている理由など、皆さんが知りたいポイントをわかりやすく整理しました。年内学力入試はMARCH以上の難関大のみを目指す方には直接関係ない可能性もありますが、併願戦略を考えるうえで重要です。どんな対策をすればよい、受験するメリットとデメリット、受験する場合の注意すべき点までを網羅し、客観的な理解につなげます。
- 年内学力入試の全体像と最新動向:誕生の背景から実例まで
- 攻略ガイド:年内学力入試の配点・戦略・準備
年内学力入試の全体像と最新動向:誕生の背景から実例まで
- そもそも「年内学力入試」とは何か?
- なぜ今、大きな話題に?「パンドラの箱」を開けた東洋大学
- 文部科学省の「待った!」と、その後の大議論
- 激しい議論の末に生まれた新ルール
- 各大学の対応は? 2026年度入試の具体例
そもそも「年内学力入試」とは何か?
まず、従来の大学入試の仕組みを簡単に説明します。これまでは、筆記試験による学力テストを2月以降に実施するルールがありました。それより前の年内(12月まで)に行う推薦入試や総合型選抜では、面接や小論文などで合否を決めていたのです。
ところが「年内学力入試」は、その名の通り年内に数学や英語といった学力テストを実施します。「推薦入試なのに筆記試験がある」など、これまでと違う入試スタイルが要点です。
実は、この年内学力入試は関西地方では全く珍しくありませんでした。近畿大学が1968年から56年間も続けており、関西では「当たり前」の入試方法だったと考えます。近畿大学だけで毎年5万人もの受験生が志願するほど定着していました。
しかし首都圏では、これまでこうした入試はほとんどありません。だからこそ、2025年度に東洋大学が首都圏で初めて大規模に実施した際、大きな話題になりました。
なぜ今、大きな話題に?「パンドラの箱」を開けた東洋大学
2025年度入試で、東洋大学と大東文化大学が首都圏初の本格的な年内学力入試を実施しました。特に東洋大学の入試には、約2万人もの受験生が殺到したのです。募集人員578人に対して2万人が応募した事実から、その注目度の高さが分かります。
この大きな反響に、大学関係者は「首都圏でパンドラの箱を開けた」と評しました。パンドラの箱とは、一度開けると後戻りできない大きな変化が起こるという意味の言葉です。まさに、この東洋大学の入試が首都圏の大学入試を大きく変えるきっかけになりました。
なぜこれほど多くの受験生が集まったのでしょうか。理由の一つは、従来の推薦入試と異なり、普段の授業で習う学力がそのまま活かせる効率の良さです。また、年内に合格が決まれば安心して残りの高校生活を送れ、万が一不合格でも2月の一般選抜へ気持ちを切り替えられます。
文部科学省の「待った!」と、その後の大議論
ところが、この東洋大学の入試に文部科学省は「待った」をかけました。従来のルールでは個別の学力検査を2月1日以降に実施することになっており、年内の学力テストは事実上の「禁じ手」とされていたためです。
文部科学省は東洋大学などを呼び出して指導し、2024年12月24日には全国の大学へ「ルールを守るように」と異例の通知を出しました。クリスマスイブという日に厳しい通知を出した事実は、文部科学省がいかに本気だったかを物語っています。
しかし実際は、従来のルールに曖昧な部分もありました。「個別学力検査は2月以降」と決まる一方、推薦入試では「各教科・科目に係るテスト」を使ってもよいと記載があったのです。この二つのテストの違いが曖昧だったため、大学側は「適性検査だから問題ない」と解釈していました。
文部科学省は「違反」とみられる全大学に個別に連絡し、募集要項をチェックする専門職員まで配置したそうです。大学の入試情報サイトを常時監視していたというのですから、その徹底ぶりがうかがえます。
そこで文部科学省は2025年3月、専門家が集まる「大学入学者選抜協議会」を開きました。この会議で、年内の学力試験実施について本格的な議論を行ったのです。
大学側からは「面接だけでは基礎学力が分からない」「関西では何十年も実績がある」といった意見が多数出ました。一方、文部科学省は「年内入試が一般選抜の前倒しになってはいけない」と考えていたのです。
激しい議論の末に生まれた新ルール
この激しい議論を経て、文部科学省は2025年6月3日に大きな方針転換を発表します。「令和8(2026)年度大学入学者選抜実施要項」の中で、条件付きで年内学力入試を容認しました。
新しいルールの内容は、年内に学力テストを行う場合、志望理由書や面接などを「必ず」組み合わせて「丁寧に」評価しなければならない、というものです。「必ず」「丁寧に」という言葉に、文部科学省の強い意思を感じます。
つまり、「学力テストだけで合否を決めるのは認めない。しかし他の要素と組み合わせ総合的に判断するなら認める」ということになったのです。これは、年内学力入試が一般選抜の単なる前倒しにならないよう、大学側に釘を刺すメッセージでした。
各大学の対応は? 2026年度入試の具体例
この新ルールを受け、多くの大学が2026年度入試での年内学力入試実施を発表しています。気になる具体的な内容を見ていきましょう。
東洋大学:学力テスト9割の配点
まず、話題の中心となった東洋大学です。2026年度は「総合型選抜 基礎学力テスト型」を11月30日に実施します。学力テスト(200点)に加え、事前提出の小論文(10点)と調査書(10点)を組み合わせた多角的評価で合否を判定する予定です。
注目すべきは配点で、学力テストが91%を占めます。400字以内で入力する小論文は配点が低いものの、東洋大学は「しっかりと採点する」と明言しています。また、試験会場を全国20箇所に拡大するため、地方の受験生も受験しやすくなります。
神奈川大学:高校の成績を重視
次に、神奈川大学は「総合型選抜(適性検査型)」を11月16日に実施します。学力テスト(200点)に調査書の評定平均値を10倍した点数(最大50点)と自己推薦書を組み合わせます。評定平均値が高い生徒は学習習慣も身についている、と大学側が判断しているためです。
大東文化大学:入学金納入期限が長い
昨年注目された大東文化大学は、「総合型選抜(基礎学力テスト型)」を11月23日に実施します。学力テスト(200点)に加え、調査書(25点)と小論文(25点)で評価します。最大の特徴は、入学金の納入期限が2月25日までと長いことです。一般選抜の結果を見てから進学するかどうかを決められるため、受験生に非常に有利な制度です。
共立女子大学:「腕試し」に最適
共立女子大学は9月28日という早い時期に「基礎力判定方式」を実施します。高校2年次までの基礎学力を測るテスト(100点)に、調査書(10点)と事前課題(10点)を組み合わせます。面白いのは、合格発表前にテストの得点と全体順位を開示する点です。これにより、一般選抜を受ける予定の生徒も「腕試し」として受験しやすくなっています。
昭和女子大学:英検で試験免除も
昭和女子大学も2026年度から「公募制推薦入試 基礎学力テスト型」を11月に導入します。この大学の特徴は、英検などの外部英語検定試験を活用した試験免除制度です。例えば英検準1級レベルのスコアがあれば英語の点数を100点に換算し、試験を免除します。検定料の割引制度も充実しており、併願しやすい仕組みが整っている点も魅力です。
関東学院大学:合格後も挑戦できる
最後に関東学院大学は、2025年度から導入した「基礎学力評価型」を2026年度も継続予定です。注目すべきは「チャレンジ・スカラシップ制度」になります。年内入試で合格した生徒が2月の一般選抜に挑戦し、好成績なら授業料が全額免除される制度です。年内に合格を確保した生徒に勉強を続けてもらうことが目的で、2月の成績が悪くても合格の権利は失いません。
※名称や設計は年度により更新されます。正式な呼称・配点・評価観点は、各大学の最新要項で確認してください。
攻略ガイド:年内学力入試の配点・戦略・準備
- 配点から見える実態は「学力重視」
- 今後どうなる?大学受験の「二極化」
- 年内学力入試は受けるべき?メリット・デメリットを比較
- 【結論】あなたのタイプに合わせて戦略を立てよう
- 中高生・保護者が今すべきこと
- まとめ:新時代の大学入試に向けて
配点から見える実態は「学力重視」
新ルールでは小論文などの組み合わせが必須になりましたが、実際の配点は興味深い現実を示します。東洋大学では学力テストが91%、神奈川大学と大東文化大学でも80%を占めています。
この配分を見ると、実質的には「学力重視の入試」です。ただし、各大学は「配点は低くても、しっかりと評価する」と強調しています。文部科学省が求めた「多面的評価」の条件は満たしつつも、学力テストの結果が合否に大きく影響することは間違いありません。
意外にも、高校現場からは歓迎の声も聞かれます。ある高校の先生は「年内に試験があると、一般選抜組の生徒の気が引き締まるのでありがたい」と語っています。
今後どうなる?大学受験の「二極化」
専門家は、この変化で大学受験が二つのパターンに分かれると分析します。
一つ目は、年内学力入試で合格を決める「年内合格組」です。早めに進路を確定させたい、安定志向の受験生がこのパターンを選ぶでしょう。
二つ目は、最後まで一般選抜で難関大学を目指す「一般選抜組」です。より高いレベルの大学を狙う、チャレンジ精神旺盛な受験生がこのパターンになります。
MARCHや関関同立以上の難関大学は、一般選抜で優秀な学生を確保できるため、年内学力入試の導入を見合わせると考えられています。一方、それ以外の大学では、早期に一定レベルの学生を確保できる有効な手段として、導入を積極的に検討するでしょう。
現在、私立大学入学者の59.3%が総合型・推薦入試で入学しており、この割合は年々上昇しています。年内学力入試の解禁でこの傾向はさらに加速します。「大学全入時代」が本格化する中で、2026年度は「大学サバイバル元年」でもあるのです。
年内学力入試は受けるべき?メリット・デメリットを比較
「自分の子どもは年内学力入試を受けるべきか」と悩みますよね。これは単純にYes/Noで答えられる問題ではありません。受験生一人ひとりの状況で最適な選択は変わるためです。判断の助けとなるよう、メリットとデメリットを整理しました。
受けることで得られる5つのメリット
- 精神的な安心感を得られる
年内に合格を勝ち取れる可能性があり、進路が早く決まれば心に余裕が生まれます。 - 一般選抜の「腕試し」になる
多くの入試は併願可能なため、本番の雰囲気を経験する絶好の機会になります。 - 受験戦略が立てやすくなる
年内入試の結果次第で、一般選抜でどの大学に出願するか戦略を柔軟に調整できます。 - 普段の勉強が活かせる
特別な対策が必要な小論文などと違い、学力テストなら普段の勉強が直結します。 - 金銭的なメリットもある
大東文化大学のように、入学金の納入期限を一般選抜後まで待ってくれる大学もあります。
知っておくべき4つのデメリットと注意点
- 対策が中途半端になるリスク
一般選抜の勉強と出願準備を並行する必要があり、どちらも中途半端になる可能性があります。 - 不合格だった場合の精神的ダメージ
「腕試し」と割り切っていても、不合格という結果は想像以上に気持ちを落ち込ませるかもしれません。 - 「燃え尽き症候群」の可能性
早く合格が決まったことで安心し、その後の学習意欲が低下してしまうケースも考えられます。 - 第一志望の選択肢にはなりにくい
難関大学は実施しない可能性が高く、あくまで「滑り止め」や「腕試し」の位置づけになります。
【結論】あなたのタイプに合わせて戦略を立てよう
結局、年内学力入試を受けるべきかは「何を優先するか」によります。
- <Yes!受けた方がいいかも>
- 早く進路を決めて安心したい「安定志向」の人
- 志望校レベルの大学がこの入試を実施している人
- 本番の空気に慣れておきたい人
- <No!慎重に考えた方がいいかも>
- 難関大学の一般選抜に100%集中したい「挑戦志向」の人
- 複数のことを同時に進めるのが苦手な人
- 一度の失敗を引きずってしまう人
自分の学力や性格、志望校のレベルを冷静に分析し、家族や先生とよく相談してベストな道を選んでください。
中高生・保護者が今すべきこと
この大きな変化の中、中高生と保護者は何をすべきでしょうか。
まず最も重要なのは情報収集です。大学は7月31日までに入試内容を公表するので、志望校の公式サイトを定期的にチェックしてください。次に、年内入試をどう活用するか受験戦略を練り直すことが必要です。
学力面では、基礎学力の向上を重視しましょう。年内入試では「高校2年次までの基礎学力」を問う大学が多いようです。また、調査書の評価に影響するため、定期テストの成績向上も忘れないでください。英検などの外部検定も有利に働く可能性があります。
最後に、スケジュール管理を徹底することが重要です。年内入試と一般選抜の両方を見据えた学習計画を立て、出願準備を進めてください。
まとめ:新時代の大学入試に向けて
年内学力入試の解禁は、大学入試の「ターニングポイント」です。これまでの単純な図式が崩れ、より複雑で多様な入試制度が生まれます。
しかし、これは受験生にとって選択肢が増える良い変化です。自分に合った入試方法を選べるようになり、早期に安心を得られる可能性も広がります。
大切なのは、この変化を恐れず、正しく理解して戦略的に活用することです。情報収集を怠らず、自分の強みを活かせる入試方法を見つけ、悔いのない受験にしてください。中学生の皆さんは、今から基礎学力を固め、将来の選択肢を広げておくことが何より大切です。
※この記事は2025年9月時点の情報に基づいています。最新の入試情報は必ず各大学の公式サイトでご確認ください。
まとめ 年内入試 学力型の要点
- 2026年度から「年内学力入試」が本格的に始まる
- 推薦・総合型選抜で、年内に学力テストを実施する
- 学力テストだけでなく小論文や面接との組み合わせが必須
- 配点は学力テスト重視(8割以上)の大学が多い
- 難関大学は導入に消極的で、中堅大学が中心となる
- 最大のメリットは、早期に合格が決まる精神的な安心感
- 一般選抜の「腕試し」として活用する戦略も有効
- 対策の中途半端化や、不合格時のダメージに注意
- 自分の学力や性格に合うか冷静に判断することが重要
- まずは大学公式サイトで最新の入試情報を必ず確認する