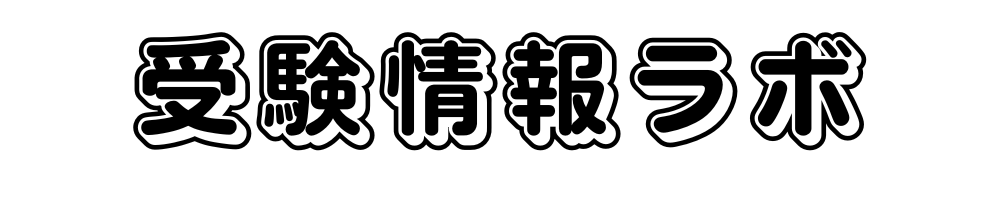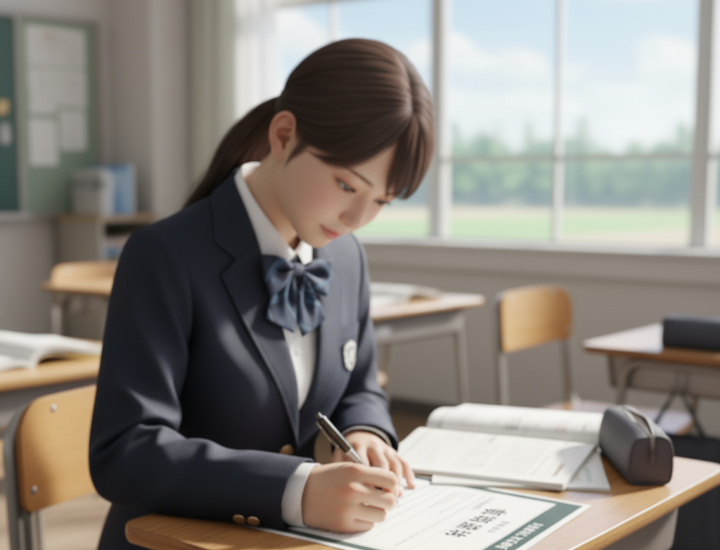志望理由書、いざ書こうとすると「何から始めよう…」とペンが止まってしまうこと、ありますよね。特に総合型選抜を考えているなら、避けては通れない壁です。どんな書き出しがいいのか、そもそも全体の書き方はどうすれば良いのかと悩んだり、参考になる良い例を探したり。ついやってしまいがちなNG例や、「である・ですます」調の使い分けまで、気になることはたくさんありますよね。でも、安心してください。この記事では、そんなあなたのための志望理由書を書くコツを、一つひとつ丁寧に解説していきます。
- 志望理由書がなぜ重要なのかがわかります
- 好印象を与える構成と準備の進め方
- 今すぐ使える具体的な書き方のコツ
- 学部別のポイントと避けるべきNG表現
評価を高める志望理由書の準備
- 総合型選抜で志望理由書が重要な訳
- まずは自己分析と大学研究から
- 志望理由書の基本的な書き方
- 志望理由書の印象を決める書き出し
総合型選抜で志望理由書が重要な訳
「なぜ志望理由書はこんなに大事なのですか?」と疑問に思うかもしれませんね。
総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜では、学力テストだけでは測れない「あなたらしさ」や「やる気」を大学に伝えるための、非常に大切な書類なのです。
これはただの作文ではなく、大学への熱意を伝える手紙のようなもの。ご自身の熱意を伝える絶好のチャンスです。
面接でも、この志望理由書に書かれた内容をもとに質問されることがほとんどです。ですから、しっかりとご自身の言葉で書いておくことが、合格への大きな一歩になるのです。
志望理由書の3つの役割
- 学習意欲のアピール:「この大学で学びたい!」という強い気持ちを伝えます。
- 人柄や価値観の提示:あなたがどんな人で、何を大切にしているかを知ってもらいます。
- 将来性の証明:大学での学びを通して、将来どう社会に貢献したいかを示します。
つまり、点数だけではない「あなた」という人間を大学にプレゼンテーションする、最強のツールということです。
まずは自己分析と大学研究から
いきなり書き始める前に、絶対にやっておきたいのが「自己分析」と「大学研究」です。この2つが志望理由書の骨格になるため、じっくり時間をかけましょう。
「自分は何が好きで、将来どうなりたいのだろうか?」
「この大学のどこに惹かれたのだろうか?」
この2つの問いに答えることが、説得力のある文章を作るカギです。
STEP1:自分を深掘りする「自己分析」
まずは、これまでの経験を振り返って、ご自身の「好き」や「得意」を見つけ出しましょう。難しく考える必要はありません。下の表のように、簡単な質問に答える形で書き出してみるのがおすすめです。
| 質問 | 書き出すこと |
|---|---|
| 過去:どんな経験をしましたか? | 部活で頑張ったこと、文化祭の思い出、印象に残った本や映画、悔しかったこと |
| 現在:何に興味がありますか? | 好きな教科、趣味、今気になっている社会問題、得意なこと |
| 未来:どうなりたいですか? | 将来つきたい職業(ぼんやりでもOK)、挑戦したいこと、どんな大人になりたいか |
STEP2:大学の魅力を知る「大学研究」
次に、志望する大学の情報を徹底的に調べましょう。パンフレットや公式サイトを見るのはもちろんですが、「なぜ他の大学ではいけないのか」を言えるくらい詳しくなるのが目標です。
大学研究のチェックリスト
- アドミッション・ポリシー:大学がどんな学生を求めているか。
- カリキュラム:どんな授業やゼミがあるか。特に興味のある教授はいるか。
- 大学の特色:留学制度、独自のプログラム、施設や設備など。
- 卒業後の進路:どんな先輩たちが、どんな場所で活躍しているか。
この2つの分析で出てきた点を線でつなげると、「私にはこのような経験や興味があり、それを実現できるのは貴学だけです」という、あなただけのストーリーが見えてくるはずです。
志望理由書の基本的な書き方
準備ができたら、いよいよ構成を考えていきましょう。文章が苦手な人でも、基本的な型を知っておけば、スムーズに書けるようになりますよ。
一般的には、次の3つの要素を盛り込むと、まとまりの良い文章になります。
志望理由書の基本構成
- きっかけ(過去):なぜその学問分野に興味を持ったのか
- 大学で学びたいこと(現在):その大学・学部で何をどう学びたいのか
- 将来の展望(未来):大学での学びを将来どう活かしたいのか
この「過去→現在→未来」の流れを意識すると、話に一貫性が出て、読み手にあなたの成長ストーリーが伝わりやすくなります。
文章の量としては、指定文字数のうち、「きっかけ」が2〜3割、「大学で学びたいこと」が5〜6割、「将来の展望」が2割くらいを目安にすると、バランスが良くなりますよ。
志望理由書の印象を決める書き出し
書き出しは、読んだ人の心を掴むための最重要ポイントです。ここで「お、この学生の話は面白そうだ」と思わせることができたら、半分は成功したようなものです。
いくつかパターンがありますので、ご自身に合ったものを選んでみてください。
パターン1:「将来の夢」から始める
一番ストレートで、熱意が伝わりやすい書き方です。「私は将来、〇〇になりたいです」と結論から示すことで、目的意識の高さをアピールできます。
例:「私は将来、AIを活用して多くの人が暮らしやすい社会を実現するエンジニアになりたいです。」
パターン2:「問題提起」から始める
社会問題などへの強い関心を示す書き方です。「現代社会には〇〇という問題があります」と切り出すことで、知的な探究心や社会貢献への意欲を伝えられます。
例:「フードロス問題が深刻化する中で、私は食の観点から持続可能な社会づくりに貢献したいと考えています。」
書き出しで注意したいのは、「貴学の素晴らしい校風に惹かれました」のような抽象的な表現です。具体性がないと、どの大学にも言える内容だと思われてしまうため気をつけましょう。
あなたらしさが一番伝わる書き出しはどれでしょうか。ご自身の言葉で、最高のスタートを切りましょう。
伝わる志望理由書にするテクニック
- 評価される志望理由書を書くコツ
- 志望理由書はである・ですます統一
- 学部別の志望理由書の例を参考に
- 避けるべき志望理由書のNG表現
- ポイントを押さえ志望理由書を完成
評価される志望理由書を書くコツ
構成や書き出しが決まったら、次は内容のクオリティを上げるコツを見ていきましょう。ちょっとした工夫で、他の人とは違う、キラリと光る志望理由書になります。
コツ1:とことん「具体的に」書く
「頑張りました」「感動しました」だけでは、あなたの気持ちは伝わりません。「どう頑張ったのか」「何に感動したのか」を、具体的なエピソードや数字を交えて書くことが大切です。
- △:部活動を頑張り、チームワークの大切さを学びました。
- 〇:〇〇部の副部長として、毎日ノートに練習メニューを記録し、部員30人の意見調整に努めた結果、チームを県大会出場に導きました。
コツ2:「あなただけの理由」を伝える
大学研究で見つけた「その大学ならではの魅力」と、自己分析で見つけた「自分らしさ」を結びつけましょう。「〇〇教授の△△という研究に興味があり、私の□□という経験を活かして学びを深めたいです」のように書けると、説得力が格段にアップします。
「なぜ、私なのか」と「なぜ、この大学なのか」の2つの問いに、ご自身の言葉で答えられているか、常にチェックしながら書くのがポイントです。
志望理由書はである・ですます統一
文章のトーンを決める「文末」。どちらを使えばいいか迷いますよね。基本的には、どちらかにしっかり統一することが一番大切です。
「です・ます」調の特徴
丁寧で、柔らかい印象を与える、最も一般的な書き方です。指定がなければ、「です・ます」調で書いておけばまず間違いないでしょう。読み手に対して誠実な気持ちが伝わりやすいのです。
「だ・である」調の特徴
断定的で、力強く、知的な印象を与える書き方です。論文などで使われることが多いですが、高校生が使うと、少し背伸びしているように見えたり、冷たい印象を与えたりする可能性もあります。自信があるテーマなら効果的かもしれませんが、基本的には「です・ます」調が無難です。
絶対に避けたい「混在」
一番やってはいけないのが、「〜です。」と書いた次の文で「〜である。」と、文末がバラバラになることです。文章全体のリズムが崩れて、とても読みにくくなってしまいます。書き終えたら、必ず声に出して読んで、文末が統一されているか確認しましょう。
どちらの文体を選ぶにしても、「相手に敬意を払い、自分の考えを明確に伝える」という意識を忘れずに、最後まで一貫したトーンで書き上げましょう。
学部別の志望理由書の例を参考に
志望する学部によって、アピールすると効果的なポイントは少しずつ違います。ここでは、学部ごとのポイントをいくつか紹介しますね。ご自身の志望学部に合わせて、内容をアレンジしてみましょう。
経済学部・経営学部
身近な経済活動への関心がアピールポイントになります。たとえば、近所の商店街の活性化策や、好きな商品のヒットの理由などを自分なりに分析し、大学で学びたいミクロ・マクロ経済学やマーケティング理論と結びつけてみましょう。
文学部・国際関係学部
なぜその言語や文化、歴史に興味を持ったのか、具体的な原体験を語ることが大切です。一冊の本、一本の映画、留学経験など、あなただけのきっかけを深掘りして、大学での研究テーマにどう繋げたいかを伝えましょう。
工学部・理学部
「〇〇という社会問題を、△△の技術で解決したい」というように、具体的な課題解決への意欲を示すのが効果的です。高校の探究活動や、科学コンテストへの参加経験などを盛り込み、大学の研究室で挑戦したいことを明確に伝えられると良いでしょう。
これらのポイントはあくまで一例です。大切なのは、あなたの「知りたい」「解決したい」という純粋な好奇心を、志望学部の学びとしっかり結びつけることです。
避けるべき志望理由書のNG表現
せっかく良い内容を書いても、ちょっとした表現でマイナスな印象を与えてしまったらもったいないですよね。ここでは、多くの人がやりがちなNG例を紹介しますので、ご自身の文章をチェックしてみてください。
志望理由書NGリスト
- 抽象的なほめ言葉:「貴学の伝統に惹かれ…」など、パンフレットに書いてあるような言葉だけでは熱意は伝わりません。
- 受け身な姿勢:「学ばせていただきたい」という表現は、主体性がない印象を与えることも。「〇〇を積極的に学びたい」という能動的な姿勢を見せましょう。
- 実績の羅列:「〇〇で1位を取りました」「資格を取りました」という事実だけを並べてもNGです。その経験から何を学び、大学でどう活かすのかを書くことが重要です。
- ストーリーの欠如:過去の経験、大学での学び、将来の夢がバラバラで繋がっていないと、一貫性のない人だと思われてしまうかもしれません。
- 誤字・脱字:言うまでもなく、基本的なミスは「注意力が足りない」という印象になります。何度も見直すのはもちろん、先生や家族など、第三者にも読んでもらうのがおすすめです。
自分では気づきにくいミスもあるため、必ず誰かに読んでもらうこと。客観的な意見をもらうことで、文章はもっともっと良くなります。
ポイントを押さえ志望理由書を完成
-
- 志望理由書は総合型選抜等の合格を左右する最重要書類の一つ
- 学力だけでは測れないあなたの個性や熱意を伝えるチャンス
– 面接の土台にもなるので自分の言葉でしっかり書くことが重要
- 執筆前には「自己分析」と「大学研究」を徹底的に行う
- 自分史やマインドマップで過去・現在・未来を深く掘り下げる
- なぜその大学でなければならないのかを言えるまで調べる
- 基本構成は「きっかけ→大学での学び→将来の展望」で一貫させる
- あなただけの成長ストーリーとして過去から未来を線で繋ぐ
- 書き出しは将来の夢や問題提起から始めると印象に残りやすい
- 具体的なエピソードや数字を交えて説得力を持たせる
- その大学だけの魅力とあなた自身の経験や目標をしっかり結びつける
- 文末は「です・ます」調に統一するのが基本で最も安全
- 学部ごとにアピールすべきポイントを意識して内容を調整する
- 抽象的な表現や受け身な姿勢は避けて主体性を示す
- 誤字脱字は絶対にNG、提出前は必ず第三者に読んでもらう